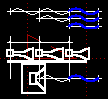SALogic solution

アナログオーディオのテクノロジーの限界から、暗黙のうちに放置されてきた
時間や位相の歪に焦点を絞り、お客様のかかえるさまざまな問題を適切な製品の開発により解決し、
理論と検証によるトータル・ソリューションをご提供します。
本稿のテーマは
ルームアコースティックとフェーズレスポンスの最適化です。

サーロジック・ソリューション
第一章
★☆★ 1. 生音とスピーカーでは指向特性が違う ★☆★
「楽器の音は四方八方の空間に拡がる360度指向性の点音源である」
と発想を転換してオーディオルームの壁面の反射と吸音のバランスを見直すと、
音を反射させるべきエリアと吸音させるべきエリアがおのずと見えてきます。
無響室や野外では生楽器は鳴りません、生楽器が生々しく鳴ってくれる音空間は、
楽器が奏でたエネルギーの倍音を含めた周波数分布のバランスが、
残響音の減衰の過程で変化しないまま滑らかに消滅してくれる
残響特性を持ったホールまたは室内です。
少なくとも、これからホールの隅々に拡がろうとしており、
充分なエネルぎーを保有している最初の反射で
空気の中を通過するだけでも自然減衰してしまう
高音域のエネルギーを失うことだけは避けなくてはなりません。
スピーカーに置きかえれば、スピーカーの後ろの壁面で
高音域のエネルギーを失うことは絶対に避けなければなりません。
コラム1
単一指向性のスピーカーでは、後方は低音過多ですから、後ろの壁面では、むしろ
中高音を増強してやるくらいの音処理が必要なことがご理解頂けると思います。
拡散音の中高音であれば、楽器の定位は、むしろ向上します。
★☆★ 2. 360度指向性スピーカーの音を普通のスピーカーで体験する ★☆★
後ろ向きにスピーカーを追加してみる、などの工夫をすると、現在お持ちのスピーカーシステムで
360度指向性の再生音に近いものを体験することができます、
もっと簡単にというのであれば、
中高音をランダムに反射する音響調整パネルをスピーカーの後ろに置いて下さい、
LV1200 StainVeil1200
後ろ向きにスピーカーを設置する以上に360度指向性の再生音に近いものを体験することができます。
ところで360度指向性は無指向性と表現することもできます、
無指向性をイメージすると、ピンポイントの定位が失われるように錯覚するのですが、
フェーズ・レスポンスを厳密に合わせた無指向性スピーカーは、
単一指向性スピーカーを超えるリアルで立体的なピンポイントの定位が実現されます。
360度指向性 スピーカー・システム
ホーンスピーカーの歴史が指向特性改善の歴史であったことからも推測できるように、
指向角を更に広げた360度指向性のスピーカーシステムが、
オーディオ再生にとって
重大な意味を持っているかもしれない、と言う事は想像の範疇であろうと思います。
もちろん想像だけではなく、DSPでフルフラットを実現した360度指向性
スピーカーシステムを製作し、試聴を重ねた結果の結論です。
360度指向性スピーカーのプロトタイプ

ピンポイントの立体的な定位を実現するには、デジタル・プリアンプとFIR方式の
デジタル・チャネルデバイダーでドライブすることが必須の条件ですが ・・・。
★☆★ 3. ホーン・スピーカーは、タイムアライメントと
位相を合わせると、本領を発揮する ★☆★
そして、360度指向性スピーカーのためのフル・デジタルの制御システムは、
位相制御の難題のために減少傾向にあるホーン・タイプのスピーカーを蘇らせ、
真の実力を引き出す制御系として、そのまま利用できるのです。
ホーンスピーカーの宿命は「時間」と「位相」整合の難しさと、
「狭い指向特性」です。
上下方向の指向性も広くなければ、
ライブハウスや、コンサートホールの臨場感の再現は曖昧になります。
LCネットワーク & アナログ・チャネル・デバイダーでは、
時間、位相ともに最適化不可能です。
IIRタイプのデジタル・チャネル・デバイダーを使うと、
クロスポイントのタイムアライメント(時間)は整合可能ですが、
ポイント周辺の位相は合いません。
FIRタイプのデジタル・チャネル・デバイダーを用いることでのみ、
タイムアライメント(時間)と位相を完璧に合わせることができるのです。
指向特性は背面に拡散パネルを置いて調整します。
360度指向性スピーカーと、指向特性の狭さでその対極に位置するホーンタイプのスピーカーが、
アナログオーディオでは不可能であった位相の難題を解決することで、
音楽再生用として最高のスピーカーシステムになるであろう予感が
オーディオを志した技術屋の興味をそそらない筈はありません。
★☆★ 4. 360度指向性スピーカーで調整した音空間は、
普通のスピーカーにも最適な音空間 ★☆★
LV1200(FW1200)パネル、スカラホール(天井吸音体)を使って
 |
360度指向性スピーカーに最適な音空間を作るには、
生楽器(360度指向性)を鳴らすことを目的に設計されているコンサート・ホールの音響処理を
オーディオルーム用に最適化すれば良いことが分かります。
1980年代のバブル時期にたくさんの体験をしましたから、近頃の
ホール設計でミスは無いと思いますが、
石やコンクリートで作られたコンサートホールの中に
非常に音の悪いものがときどき混じっていました。
一般に石作りのホールは、最高の音楽を奏でるタイプと、音楽を殺してしまう
タイプに大きく分かれます、そこそこの中庸がありません。
一方木作りのホールは、中の上付近に固まる傾向があります。
石作りの最高と最低の分かれ目はその壁面の表面構造によるもので、
平行な壁面を作らないのは当然のことですが、
その表面がつるつるの平面では音は必ずNG!です、
ざっくり見れば平面であっても、その表面がタイルを貼ったり、石板を積み上げたりと
でこぼこしている場合はGoodです。
つまり、中高音をランダムに反射するか否かが、ホールの音の良し悪しを決定するのです、
乱反射により、客席が中高音の残響エネルギーで充満されるホールは
音楽を楽しむことができる楽しい音のホールになります。
空気減衰による中高音の不足を乱反射音が補充してくれるのです。
そしてこの処理が普通のスピーカーシステムにも最適な音空間であることを
360度指向性オーディオ&測定用スピーカー

の設計、試作、調整の段階で学びました。
360度方向に同じ音を発散する無指向の音源を使うと、部屋の特性の変更と、
スピーカーの音色の変化がとても良くわかります。
室内では、内装の木材・壁紙・カーテンなどが空気減衰に替わり中高音を吸収
してしまいます。
また脆弱な壁材などが低音に揺すられてスピーカー・モドキとなり、
ミッド・バスの振動音を室内に垂れ流します。
振動によるエネルギーが、ブーミングの
エネルギーを超えることも多々あります。
超低音を再生するスーパーウーファーを設置すると、壁面が振動する音が耳で聞こえる
ようになり、対策すべき部分が明確になります。
スーパーウーファーを設置するために壁面の補強が必要になるのではなく、
メインのスピーカーの実力を発揮させるために、以前から壁面の補強が必要だったのです。
補強すべき部分は壁を叩いてその音で判断します。”ゴツ”、”ド”などの
短い振動であればOK、”ドサ”、”バターン”などの長い振動が出る部分は補強が必要です。
LV1200などで覆っても良いでしょう。
★☆★ 5. 無指向性スピーカーは、生音と同じ音像定位 ★☆★
近頃はドーム型ユニットのスピーカー・システムが全盛です、
中音域の指向特性が広いスピーカーシステムはリスニングエリアが広いのが特徴で、
二等辺三角形の頂点から外れてもセンター定位が得られる点で、
家族で楽しむホームシアター向きだからです。
例えば、完全無指向性のスピーカーシステムでは、
左のスピーカーの更に外側に着座しても、ボーカルがセンターに定位します。
右のスピーカーからの直接音が耳に届くからで、
クラシックのコンサートで、左端前列の席からでも演奏者の位置が
耳で分かるのと同じ理屈です。
単一指向性のPAスピーカーを使うポップスのコンサートでは、全ての音が左端に集中してしまいます。
★☆★ 6. ホーンの優美な形状と360度指向性の高い音楽性を結び付ける ★☆★
オーディオを志したからにはオールホーンが究極の目的である、
と明言されるハイエンド・オーディオ愛好家の方も多いと思います。
ホーンスピーカーの音には捨てがたい魅力が沢山あります、
しかし二つの難題も抱えています。
その一つが指向特性です。指向特性は上下にも広くなければ生楽器の存在感を
表現することは難しくなります。ライブハウスの臨場感、録音したスタジオの空気感などの表現は
かなり割り引かれて再現されているはずです。
LV1200パネルなどで無指向性系の音を加えてみて下さい、慣れによって
気付かなくなっていたホーンスピーカーの欠点が顕になると思います。
そしてLV1200パネルが必需品になるに違いないと思います。
これで一つ目の課題が克服されました。
もう一つが位相整合の難しさです。
対称型の係数ファイルを用いた、FIRフィルターにより解決可能なことは述べましたが、
測定結果で良しとされる係数ファイルと、聴感で良しとされる係数ファイルが同じではない点で、
メーカーを悩ませる難しい製品です。
二つ目の課題も解決の糸口は見えています。

★☆★ オーディオを楽しむには、まず部屋を直しましょう ★☆★
★ 16ビット・フォーマットのCDに不足しているものを、あえて上げれば、
楽器の背景音の情報量(分解能)の不足です、
しかし、もっと不足しているものが、スピーカー・システムの背景音再現能力で、
1. ユニットの指向特性
2. ネットワークの位相特性
3. 超低音レンジの不足
が3大要因です。
サーロジック・ソリューションでは、
1. LV1200、FW1200パネル(発売中)
2. FIRのデジタル・チャネル・デバイダー(2002年発売の予定)
3. SPD−P4 + W1600(発売中)
をお勧めします。
オーディオを楽しむには、まず部屋を直しましょう ・・
そしてサーロジック製品であれば 2.または 3.に進んでください。
と言うのが
サーロジックからのご提案です。
■ 指向特性と残響時間を改善する音響調整パネルがFW1200とLV1200で、
その有効性は 2001年のうちに、たくさんの方に認めていただきました。
■ 2002年はクロスオーバーポイント周辺のタイムアライ
メントも合わせてしまうことができる、デジタルプロセッサーを発売予定です。
積和演算が高速・高精度で実行できるDSP環境が整ったことで可
能になったもので、2002年は真のオーディオ元年にできると
期待しています。
■ 既に発売しているスーパーウーファーは、生音に比べて絶対的に不足して
いる超低音を少しでも生音に近付けようと追求した結果であると
同時に、音の良いFIRフィルターの開発に不可欠な、超低音域の制御
のノウハウを蓄積する研究材料にもなりました。
低音域はFIRフィルターにとっても充分に手ごわい相手で、教科書通りの制御
では最高の音質は期待できません。
2002年にSPDシリーズを大幅に改良したスーパーウーファーの新製品を投入します、
一切の妥協を排除した新シリーズで、コストがかなりアップすると予想しています。
コスト・パフォーマンスを考慮した場合、「SPD−P4とSPD−W1600」の組み合わせを
お勧めします。大きなパワーが不要であれば「D-Cube」がお勧めです。
 |
<-- ScalarHole
天井吸音体
機能 ・・・ 全音域吸音
効果 ・・・ オーディオルームのミッド・バスの
周波数特性をフラット化する |
  |
<-- LV1200音響調整パネル
FW1200音響調整パネル -->
機能 ・・・ 低音吸収、中高音拡散
効果 ・・・ 適切に配置することにより、普通のスピーカーシステムに360度指向性スピーカーの表現力を合わせ持たせることができる |
 |
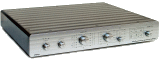  |
<-- SPD−P4デジタル・プロセッサ
<-- SPD−W1600サブウーファ-
再生帯域 ・・・ 10Hz〜65Hz、
120Hz(シアター・モード)
特徴 ・・・ 使い易さと、SPDシリーズ中で最高のクオリティーを併せ持つ
効果 ・・・ 可聴帯域以下の超低音の再生と、超低音が醸し出す音楽の背景の再現 |

サーロジック・ソリューション
第ニ章
★☆★ 1. 空気は直線位相のアナログ遅延回路である ★☆★
1.楽器が奏でた音は、大気の中を伝わる伝播時間だけ遅れて低音〜高音
までの全ての音が同時に耳に到達します。つまり耳に届いた
生音とは、
大気が媒介する直線位相のアナログディレイを通過した生音である。
つまり直線位相のディレイだけの系は音に無害なのです。
注: 直線位相とは、音の遅れ時間が周波数に無関係に一定である系を示すもので、
空気中であれば340mで約1秒(気温で変化する)の伝播時間がかかります。
10Hzでも遅れ時間は1秒、10kHzでも1秒ですから直線位相です。
1年前に製作されたCDを今日聴いても、全ての音が1年分遅れるだけで、
同時に耳に届きます、CDも直線位相です。
周波数にかかわらず、音源から同時に送り出された音が、同時に耳に届く系
のことを直線位相の系と言います。
2.オーディオ機器に非直線位相の帯域があるかぎり、生音の一部である臨場感が
欠落します、真のオーディオ再生には大気と同じ直線位相が不可
欠な要素なのです。
★☆★ 2. FIRフィルターなら直線位相が実現できる ★☆★
1.直線位相の阻害要因はLCネットワーク、アナログチャネル・デバイダー、
IIR方式デジタル・チャネル・デバイダーなどで、それらを対称型の
FIRフィルターに置きかえると直線位相が実現可能になります。
しかし
直線位相のFIRフイルターにも対称係数固有のプリエコー歪みがあり、
その回避テクニックを誤ると直線位相だが音は?・・ となります。
楽器が発するルートから高次の倍音までの全ての音エネルギーが、
同時にリスナーの耳に届くとき、ホールなどの音空間の佇まいも
含めた音楽再生が可能になります。
★☆★ 3. 聴覚と音の認識 ★☆★
近年の研究成果で、音や映像の情報は、脳に蓄積された過去の記憶と瞬
時に比較照合されて認識されることが解明されてきました。
自然界の音と、その自然界の音を音楽鑑賞に最適な響に集大成した、
コンサートホールの音に近い再生音が得られたなら、
また
再生システムの周波数特性、指向特性、位相特性を、生音のようにフラットに
することができたなら、脳の照合動作がスムーズに進行し、音楽をゆったり楽
しむ余裕が生まれます。
この状態では、聴き疲れのような音を止めたいと言う衝動は起こりません。
しかしフラットレスポンスの達成は簡単なことではありません。部屋の音響
特性も含めてフラット化しなければならないからです。
★☆★ 4. フラットレスポンスの達成に必要な、周波数と時間の知識 ★☆★
★ 周波数特性と聴覚 ★
現代スピーカーの周波数レスポンスに比べると、ビンテージスピーカーのレン
ジは狭いものが多く、個性的と言われるレスポンスのうねりを持ったものが多くあります。
しかし愛用者が多いことでも分かるように、聴覚側がフラットではない周波数
レスポンスへの適応能力を持っていることがわかります。
プロのミキシング・エンジニアでも、レコーディングの最終工程のリミックスでは、基準に
するCDと音質の比較をしたり、一晩睡眠をとってから2ミックスを仕上げるなど、
周波数レスポンスのブレを防ぐ対策を講じています。
■ 人の声などの同じ音源の同じ音が、聞く場所が変わることで大幅に変化
することを日常体験しており、照合する引出しが沢山あるのだと思いますが、
オーディオシステムの周波数レスポンスには絶対基準はなく、
個人の好みと、どこまでのクオリティーを必要と考えるかの
範疇で捉えても良いものと思います。
■ 一方で、周波数特性以外の部分に欠点が無い(F特で補う必要が無い)
システムでは、フラットレスポンスに近付くほど再生音が緻密になり、
音楽の充実度が増すことも、まぎれれも無い事実です(直線位相のデジ
タルフィルターでの実験結果)。
★ 位相特性と聴覚 ★
位相は説明がむずかしいので、二人の人間(友人と私)が一つの室内に居る
との想定でご説明します。
★ 直接音に注目すると ★
友人が正面から私に話しかけてきました、左右の耳には、同音質で等時間
の音声が届き、正面からの声であることが分かる不自然さの無い音です。
左側から話しかけられると、右耳に入る音だけ高音域のレベルが下がり時間
も遅れた音になります。左側からの音声であることが分かる不自然さの無い
音です。
★ 間接音に注目すると ★
オーディオルームを想定して、正面の壁が全面反射の板壁、左右の壁が
全面カーテンの吸音壁とします。
正面右前コーナーの、吸音と反射の境目に顔を向けているとき、友人が
話しかけた声の反射音は、
左の耳にはライブ感のある周波数特性のフラットな余韻の長い声、右の耳には
カーテンで中高音を吸われ、高音不足でかつ余韻の短い声が入ります。
一瞬ですが、左の耳には音があり、右の耳には音が無い境目のある状態が
作り出されます。
このときの違和感は、スパイの拷問にも使われた究極の境目である左右の
耳に逆位相の音が入力された時に感じる精神的圧迫感と同類のものです。
オーディオ暦が長いと、この一瞬の境目が居心地の悪さに繋がります。無意
識のうちに音楽芸術に没頭できない原因の一つになるのです。
オーディオルームの中では、大きな反射面と大きな吸音面を明確な接点で
付き合わせてはいけません。それぞれ分散配置が鉄則です。
スカラ・ホール(天井吸音体)は、

中心では100Hz以上の周波数を全吸音しますが、
端に行くに従い高音しか吸音しなくなり、天井の反射面にスムーズに
繋がる構造です。
聴覚は左右の耳に入力される音の時間差と位相差で音源の方向を判定し、
直接音と残響音の比率で音源までの距離を想像します、真横からの音であ
れば、1kHzの音は逆位相になります、
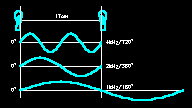
従って日常的に逆位相の音は体験
しているのですが、500Hz以下の音には逆位相成分が存在しない点に注目
しておく必要があります。
聴覚が音の時間差と位相差で音源の方向や佇まいを判定している事実から、
位相ずれを含むオーディオ・システムからは、ピンポイントの定位や立体的な
存在感が再現され得ないことがお分かりいただけるものと思います。
★ ラジカセでも位相の被害を受ける ★
ラジカセ(CDもついていますが)の音で恐縮ですが、初期のラジカセの音質
コントロールはHiとLoだけのシェルビングEQで、スピーカーはシングルコーンでした。
Hi&Loをブーストしてドンシャリにすると、本格的なオーディオシステムを越
える臨場感を再現する製品もありました。(シングル・コーンで位相特性が良かった)
1995年頃からでしょうか、DSPを使ったグラフィック・タイプの音質コントロ
ールが全盛となり、スピーカーがマルチウエイになったことも加わって音楽の
情景を楽しめるラジカセが無くなってしまいました。販売戦略に翻弄された結
果EQ・スピーカー共に位相の改悪が行われたからです。
最近はシェルビング・タイプのEQが復活して、状況がかなり改善されてきました。
位相の不具合はラジカセの音でも、深刻な影響を受けるのです。
 ★ GEQとSEQ ★
★ GEQとSEQ ★
グラフィックEQとシェルビングEQを比較すると、周波数特性の自由度でGEQ
が格段に有利で、好みの音質の再生システムが作れるに違いないと錯覚する
のですが、大きなウイークポイントがあります。
グラフィックEQではEQのポイント数だけ位相が乱れるのです。
シェルビングEQの位相遷移はゆっくり滑らかで、聴覚が不快と感じる度合いは
限りなく低いと私は思っています。
腕の良いレコーディング・エンジニアの音作り
はSEQで音質のイメージを決め、必要最小限のGEQを追加します。
グラフィックEQの位相遷移は急激でに断層ができるように変化します。この
断層から不快な気配が滲み出ることはピュアオーディオの技術者なら皆体験
しています。
★ ネットワークの位相 ★
マルチスピーカーのネットワークも位相の呪縛から逃れることはできません、
滑らかな位相の変化であれば不快感を伴わないので、
位相補正回路を付加してクロスポイントの位相を滑らかに繋ぐのですが、
カットしきれない音が残っているポインと周辺の帯域では、時間のずれた二つ
の音が存在してしまいます。あちらを立てればこちらが立たずのトレード・オフ
まがいのことをするわけで、対策が難しいのが実状です。
周波数レスポンスと位相レスポンスが個別に制御できるFIRタイプのデジタル
フィルターを使うのがネットワークの王道で間違いのない方法です。
★ 臨場感の欠如は時間に置き換えて説明できる ★
位相ズレが引き起こす臨場感の欠如は次のように説明できます。
位相の遅れを引き伸ばし拡大していくと時間の遅れとして聞き取れるようになります。
ピアニストが同時に叩いた左手と右手の鍵盤から、左手の音だけが先に客席に
届き、少し遅れて右手の音が届くとしたら、音楽が楽しめるでしょうか?
アナログまたはデジタルIIRタイプのチャネル・デバイダーのクロスポイントでは
0.5オクターブ程度の狭い音域ですが位相のミスマッチが発生し、
鍵盤の音に僅かな時間差を生みます。
2Wayなら0.5octの被害で済みますが、4Wayなら
合計1.5octで可聴帯域の15%に匹敵します、分割数の多い高度なマルチシス
テムほど被害が拡大するので要注意です。
リスニングルームの左右の壁面の間や、天井〜床の間で発生する鳴き竜
現象も、元の音楽に対して繰り返し反射するディレイ現象で、広く解釈すれ
ば時間の遅れ
-->
位相のミスマッチの範疇に入ります。
位相の呪縛からの開放がピュアオーディオに残された最重要課題で、直線
位相の対称型FIRフィルターにその可能性を見出すことができます。
FIRフィルターはCDやDVDのオーバーサンプリング・デジタルフィルターに
必ず使われており、音質的に最善であることに疑いの余地はありません。
しかしこのフィルターにも新しい形の歪みの要素があります、
デジタル信号処理理論の教科書に従って算出したインパルス応答で
低域側を処理すると、必ずしも最良の音のはなりません。
しかし、経験と聴感とアイデアを組み合わせることで、改善可能な部分です。
決定的な位相歪みを持つIIRや、アナログのチャネル・ディバイダーが
FIRのディバイダーに勝てるはずはなく、試聴の結果でIIRの音が良かったと
すれば、それは技術力とアイデアの欠乏によるものです。
★ リスニングルームにも位相歪みがある ★
リスニングルームの左右の壁面の間や、天井〜床の間で発生する鳴き竜
現象も、元の音楽に対して繰り返し反射するディレイ現象で、広く解釈すれ
ば時間の遅れ
-->
位相のミスマッチの範疇に入ります。
オーディオ再生に残された課題は、全て時間に置き換えて追求することができるものばかりです。
デジタル信号処理の独壇場です。
弊社のDSP製品は電気回路を直線
位相に保つためのアイテム、LVまたはFWパネルとScaraHoleはオーディオルームを正常
位相に保つためのアイテムです。
★☆★ 5. フラットレスポンス化の実行演習 ★☆★
このソリューションの項目は、お客様からのご質問に
お答えしたものを再編集したものです。
★☆★ やっとご質問の回答にたどり着きました ★☆★
> 何回かサーロジックのホームページを見せてもらっています。そもそも
>
雑誌で、 スーパーウーハーの記事を見て、見始めたのですが、とても注
> 目しています。私は、
>
学生時代以来、20年以上マルチアンプシステムでステレオをならすこと
> に興味が
あって、世の動向とは全く関係なく今もそれを追求しています。
> ところで、システムの核になるチャンネルディバイダーですが、今はアキュ
>
フェーズのF25Lを使って3ウェイ(クロスオーバーは70HZと1200HZ)で
>
鳴らしています。今回サーロジックのデジタルチャンネルディバイダーが
> 製品化される予定と聞いて、迷いが生じまし
た。アドバイスいただけると
> 幸いです。
>
1.サーロジックのD−cubeを追加し、アキュフェーズのチャンネルディバ
>
イダーをそのまま使用して4way化するか。
■ 今お使いのオーディオシステムに、第1章、第2章でご説明した位相歪みに起因する
不満が感じられないようであれば DCubeの追加でよろしいと思います。
DCubeによる可聴域外の超低音の追加で、新たに下記の効果が期待できます。
1.可聴域外まで低音域が拡大されることで、オーディオは所詮パッケジ音
楽、コンサートホールやライブハウスの熱気は感じられなくて当然との認識
が間違いであったことに気付かれると思います。
ライブの臨場感は可聴帯域以下の超低音の揺らぎに依存する部分が多く、
超低音の直接音とその反射音が、コンサートホールなどの閉空間において
いかなる干渉模様を繰り広げるのかを解析する必要があります。
衰退気味の従来のピュアオーディオを、
次のステップであるアクティブオーディオに変身させるためには、
その物理現象をいかにしてピュアオーディオの再生系に組み込むのか、
真剣に考えなければなりません。
2.100dB/octのローパスフィルターを通過した音はメロディーの情報を持ちません。
例えば、SW1600のPASS BANDを38Hzにして、SW1600単体で楽曲を聞いても
曲目は判別できません。
また適正レベルでは、耳に感じる音すら殆ど聞こえません(音量を上げると
スピーカーユニットの高調波歪みが増加して聞こえるようになる)。
この無音に近い状態で、スーパーウーファーの位相をメインスピーカーに合わせ(プロ
セッサーのD1、D2ノブで合わせる)、両者を同時に鳴らすと、
コンサートホールの扉を開けた瞬間に耳と身体が感じる、空気の揺らぎを
体感することになります。・・・超低音が聴こえるようになるのです。
その超低音を、たとえばAXIOM80のような超個性的なキャラクターの
スピーカーと組み合わせると、
2kHzのベークライトの共振とも思われるきついキャラクターが薄め
られるにもかかわらず、その艶っぽさは少しも減少しません、そして楽器が
演奏された場所の背景音が聞こえるようになります。
今月発売(2001年12月)のステレオサウンド誌が今しがた届きました、その中に、SW1600を評して
「コンサートに行ったときに、ロビーからホールに入った感じ」との下りがあります、
コンサートホールの客席で体感する音の抱擁感の源泉が何であるのか?
その答えは、フランスやドイツの残響時間が10秒あるかと思われる巨大な
礼拝堂を訪れると明らかになります。
礼拝堂やコンサートホールなど、ライブで巨大な閉鎖空間に発生する
超低音域の定在波によるイリュージョンと思われます。
その定在波の雰囲気をオーディオ再生でシミュレートし、
その要素を僅かにミックスしたときに、
脳に刻み込まれたコンサートホールの体験が蘇えるのです。
SPD−P4+W1600
SW1600
DigiCube1
DigiCube2
などのスーパーウーファーはピュアオーディオ&ホームシアターに
コンサートホールのイリュージョンをお届けするためのサブシステムで、聞える低音を
より誇張して聞かせようとする一般のサブウーファーとは設計思想そのものが異なるのです。
★ マルチウエイ・スピーカーシステムの位相の合わせ方 ★
ところでDCubeを増設するには、メインのシステムの位相を可能な限り正確に
合わせていただくと、その効果がはっきり認識できるようになります。
スピーカーシステムの位相は、距離による調製が最も簡単で確実な方法です。
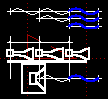
>
それとも
> 2.F25Lをやめて、サーロジックのデジタルチャンネルディバイダーを核に
>
導入し、3wayのままいくか。その場合、70HZ以下を受け持たせている
>
ウーハーが老朽化しているので、まず手始めとしてまずサーロジックのウ
>
ーハーBOXと800Wのアンプが一体化した製品を導入し、とりあえずアキ
>
ュフェーズで鳴らし、予算的に可能となった時点でデジタルチャンネルディ
> バイダーに変えるか。
弊社デジタル・チャネル・ディバイダーの発売時期に、ディバイダーにDCube
をデジタルで接続するためのアップグレードを実施いたします。
★☆★ SPDシリーズスーパーウーファーの位相の合わせ方 ★☆★
DSPによる直線位相のFIRフィルター(周波数に拘わらずディレータイムが一定)でスピーカーの
周波数特性を補正すると、フィルターのタップ長の1/2のに相当する時間、サブウーファーの音が遅れます。
動画シミュレーションのように
http://www.salogic.com/home.files/exclusive/exclusive-data.htm#move-simulation
フィルターの遅れに更にディレーを加え、その遅れがクロス周波数の1波長の整数倍に
一致するように設定すると、聴感では位相が合ったように聞えます。
この方法はホーンスピーカーの位相整合に従来から使われている手法の応用です。
http://www.salogic.com/home.files/solution/multi.htm
そして同時に更に二つのメリットを生みます。
■1.人の聴覚は僅かに時間のずれた同音量の二つの音(クロスポイントではメイン&サブ同音量)
を聴くと、先に聞こえた音の印象をより強く認識します。従ってサブウーファーを追加しても
メインスピーカーの音色が変わりません。
■2.フランスやドイツの残響時間が10秒もあるような大教会の礼拝堂では、
足元から胸まで幾十にも重なった揺らぎのような超低音の湖に浸かり、
中高音が空から降ってくるような神秘的な音を体験することができます。
そしてその音がクラシックのコンサートホールの音作りの原点である事が自ずと理解できるのです。
●つまり超低音の領域に位相のうねりがあると、コンサートホールのイリュージョンが再現される
であろう事が想像できるのです。
フェーズ・ドメイン方式はクロスポイントの位相だけを合わせる方式ですが、
クロスより上の領域は100dB/octの急峻なフィルターにより音が重ならないため、
位相干渉は起こりません。
クロスより下の領域はメインウーファーの低域の切れが甘いとき位相干渉が発生します、
しかし軽度の位相干渉による超低音の揺らぎは、コンサートホールのイリュージョンを
オーディオルームに再現するプラスの効果を発揮するのです。
SX-DW7の項の後半も参照して下さい。


![]()




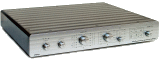

![]()