 |
D.Cube2ex 本日無事に到着致しました。早速セッティングして、調整に励んでおります。 やはり前のものと較べてふところが深いと言う印象を持ちました。それから、なんといいましょうか、加わる低域の透明感が増しているような気がするのです。 音の輪郭がボケずにスムーズに流れるというような。まだ、慣らし運転ですので、真価はこれからだと思いますが。 |
> 透明感が増しているような気がするのです
D.Cube2ex のユニットと従来のユニット(D.Cube2)を比較したときに感じる透明度の差は、振動系の歪率の違によるもののようです。ex のユニットはドライブレベルに比例して少しずつ歪が増え、破綻レベルで急増するのに対し、従来のユニットは小音量時からある程度の歪を持ち、しかし破綻レベルが不明確であるという特徴がありました(とは言え、このユニットを超えるものはなかなか見つかりません)。
また振動板エッジを支えるゴムの逆共振の影響と思われる音切れに大きな差があります。 ex のユニットでは入力の終了と同時に音が止まりますが、大きなエッジを持つ従来のユニットでは若干余韻が残ります。
実はD.Cube2のアナログ回路には、オーディオ用の古典的OPアンプで、比較的歪率の高いNE5532を採用しています(といってもスピーカーの振動系の歪率と比べれば1/100以下ですが・・)。常識的なOPアンプの選択基準に照らせば、TI(BB)のOPA627あたりを採用すべきですが、あえて高調波歪の多いNE5532を選んでいます。DSPによるLPFを通過することで、可聴限界以下の超低音だけになってしまった例えばベースの音に、おぼろげながらでも楽器の輪郭を与えようと配慮したものです。しかし僅かに見えていた輪郭はスピーカーユニットの性格によるものであったようで、D.Cube2exでは風圧のような空気の揺れを感じるのみです。
タイムアライメントが合っていない導入直後の段階では、中~小音量にすると超低音が全く聞こえないと思います、導入時のバランス設定で悩まれるケースが増えてしまうのではないか・・、と危惧しています。
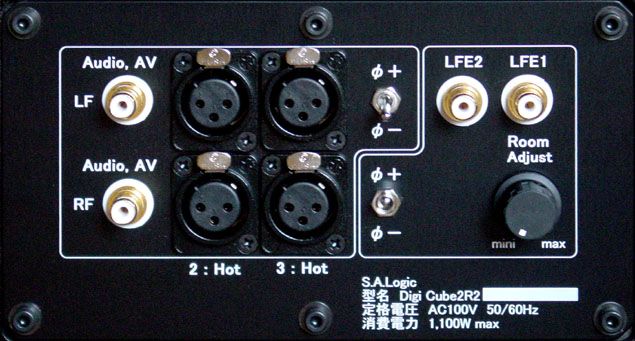
■ 数日の調整の後に頂いたレポート
2004年2月14日、ヴァレンタインズ・デーの土曜日に、チョコレートのように黒い精悍なD.Cube2EXが2台、サーロジックの村田さんから届けられました。シリアル№は光栄にも0001と0002です。
昨年の12月から先週まで、通常のD.Cube2のデモ機を2台お借りしていましたので、その2台で追い込んで決めたのと同じ場所にEXをそれぞれ設置しました。メインSPの間隔は約2mで、左右のEXの間隔は約130cmです。メインスピーカー(Avalon社のEidolon)の後方の壁面に可能な限り近い位置にインシュレーターをかまして置きます。ただし、左のEXはCDラックの分だけ前に出ており、メインSPからは左が約50cm、右が約70cm後方とずれています。もちろん、フロントパネルのタイムアラインメント機能で調整済みです。昨年届いたD.Cube2では、当初メインSPのすぐ内側に並べてみたのですが、その後、やはりメインSPより後ろの壁際に設置した方が好みの方向に効果が振れました。私は、音像の実体感も重視しつつも、可能な限り深く高くワイドに広がる音場の再生を第一に考えていますが、D.Cube2は、低音に十分なウェイトを加えてくれるだけでなく、特にユニットをメインSPの後方に置くことで、サウンドステージの拡大、特に奥行きが深くなって立体感が増すことに驚きました。
さて、EXのレベル設定は、何通りかを試し、結局、前のD.Cube2の設定とほぼ同じとなりました。インプットレベルが12時、アウトプットレベル午後1時の位置です。しかし、EXのクロスオーバー周波数は、以前の32Hzから一ステップ上げて38Hzとしました。音を出してすぐに感じたことですが、EXでは歪感が非常に少なく、澄んだ低域をもたらすようなのです。ですから、クロスオーバー周波数を上げていっても音が濁りません。いや、全域の透明感は、EXを追加することで大きく向上しているようにさえ感じました。(誤解なきよう付記すれば、通常のD.Cube2でも41Hz程度まで上げてもメインSPとの折り合いが悪くなるようなことはありませんでした。)更には、重低音がグワンと出たかと思いきや、スパッと止まる俊敏さは、EXでは更にその切れ味を増しているように感じました。
私はハンス・ジマーの映画音楽が好きで、今回も「ハンニバル」や「ラスト・サムライ」等のサントラ盤CDを使用しました。EXを入れると、音楽の抑揚の幅が大きくなり、また、CDのエッジ感が和らいで、音色は濃い方向に変化するように思います。EXを2台使用することによって、サラウンドを彷彿とさせるような豊かな抱擁感と臨場感を2chでも取り出せるのではないか、との期待が増しています。特に、オーケストラの低弦が沈み込む様や、教会の合唱における音場の広さ、高さには、思わずほおが緩みました。ただ、サントラ盤は突然異常なレベルの超低域が録音されていることが多く、あまりレベルを上げ過ぎると、心臓に悪い音(および振動板の凄まじい揺れ方)が現れるので注意が必要です。特にEXは、歪感が少ない分、音量レベルが低いと低音の存在感が薄れ気味になり、レベルを上げ気味になるので、そこをコントロールしながら、ベストの設定を探っていきたいと思っています。
(2004年2月15日 川崎 一彦)
> メインSPより後ろの壁際に設置した方が好みの方向に効果が振れました。
メインSPと正面の壁の距離を 1~3m離すと、音場感豊かで且つ分離のよい再生音が得られるケースが多いようです(部屋が広くなければ不可能ですが・・)。一方メインSPが作り出した音場をサブウーファの超低音がゆったりと包み込むように拡がるためには、壁際の設置が好結果をもたらします。
つまりメインSPのベストポジションとサブウーファのベストポジションが重なる確率は非常に低いのです。D.Cube2ではタイムアライメント調整機能でリスニングポジションからの距離の差を補正して設置します。
昨年後半から開始した訪問チューニングのキャンペーンで約50のオーディオルームを拝見させていただきました。経験値であり確固たる確信は得ていませんが、サブウーファが心地よく鳴ってくれるポジションの探し方に一定のルールがあるように感じています。
サブウーファの最適設置場所の探し方
超低音の心地よさを再現すには、サブウーファは何処に置くべきなのか? サブウーファの導入初期に必ずぶつかる大問題です・・。 かまわず無造作にセットし鳴らしてください(単体で鳴らしたほうが分かり易い)、そして超低音が豊かに且つクリアに響く場所を探し出し、サブウーファを移動します。
超低音が豊かに響く位置にサブウーファを設置すると、リスニングポイントの超低音も豊かになります。
川崎さんのHPの最後の部分に、D.Cube-2、-2ex に関するレポートがあります。
http://home.j08.itscom.net/studio-k/tcn-catv/second/kawasakisecond.html
■ 追加レポート
2月24日、修理に出していたジェフロウランドのモデル12が戻って来たので、岡島さんからお借りしていた氏自作パワーアンプと入れ替えました。アンプのゲインが異なるためメインSPからの音量が上がり、既存の設定ではEXからの音量が不足します。そこで、クロスオーバー周波数は38Hzのまま、EXの入力と出力レベルを調整し、入力は12時から3時へ、出力も1時から2時の位置へアップさせました。
これでバランスがとれ、試聴用CD数枚を気持ちよく聴いていたのですが、確認のためマニュアルで推奨のセリーヌ・ディオンの曲をかけました。すると「ドゥーーン」と鳴るべき最低音の再生個所でEXのSPユニットが追随できないのか、「ドワドワドワ」と波を打ちます。タイムアラインメントを変更しても変わりません。クロスオーバー周波数を38Hzから41Hzに上げてみると、症状は余計にひどくなります。そこで、逆にクロスを32Hzへ下げたところ、きれいな「ドゥーーン」が聴こえて来ました。
その後、セリーヌの曲以外でもクロスオーバー周波数や出力レベルが高いと超低域が録音されている個所で破綻寸前のCDが若干出てきました。EXではクロスを41Hzまたは44Hzまで上げて使えるかな、と少し期待していたのですが、現在のモデル12とのマッチングにおいては、超低域の録音レベルが高いいくつかのCDでは、クロスを上げるとクリアできない個所が出てきてしまうという結果でした。最適な設定を追い込むとすれば、その設定は各CD、もしくは曲ごとに異なるかも知れません。とは言うものの、クロスオーバー周波数32Hz(入力3時、出力2時)で、ほぼ全てのCDから相当に高いD.Cube効果を得られるので、現在これで固定して聴いています。スケール感、立体感がよく出ますし、音像と音像の間が気持ちよく離れてくれ、音が視覚的にも楽しい、と言った感じで展開します。バランスがよくなったので、聴く音量は全体に下がり気味です。小音量でも大きなサウンドステージで音が展開するので満足できるようです。
LP再生におけるEX
CDの調整が一段落したので、LP再生に移ります。CDと同じ設定でスタートし、出力レベルだけ0にして、これを徐々に上げていきます。LPの場合、出力レベルが12時を回るとSPユニットの揺れがかなり大きくなります。しかしCDとは異なり、破綻の前触れのような音が出ている訳ではありません。ただ単に、見ていると壊れそうで心臓に悪い揺れということです。そこで、CDと同じくらいの揺れに見た目で合わせて、出力を11時とします。
これで各種LPを次々かけていきますが、D.Cubeを付加した効果はCDと同様に至る所に現れます。スケール感、安定感、立体感、滑らかさ、生々しさ。ただし、ソリッドで硬質な方向は抑えられますので、JAZZやROCKでの曲によっては無い方がよいとも思いました。これでクロスオーバー周波数を41Hz、44Hzと上げてみましたが、ちょっと下が厚くなり過ぎるようで、32Hzに戻しました。